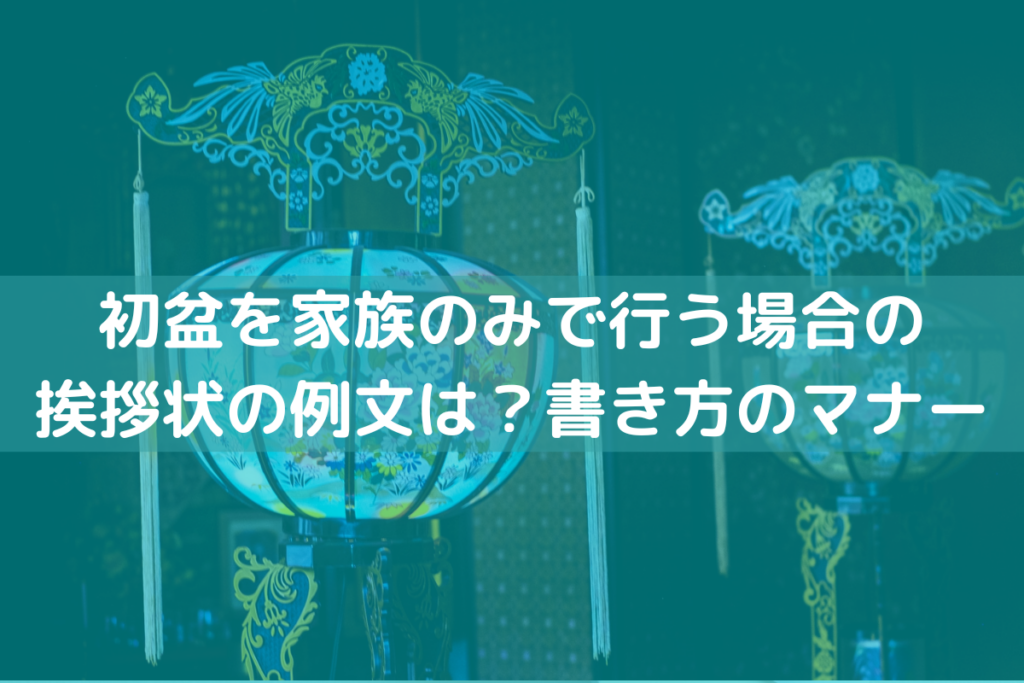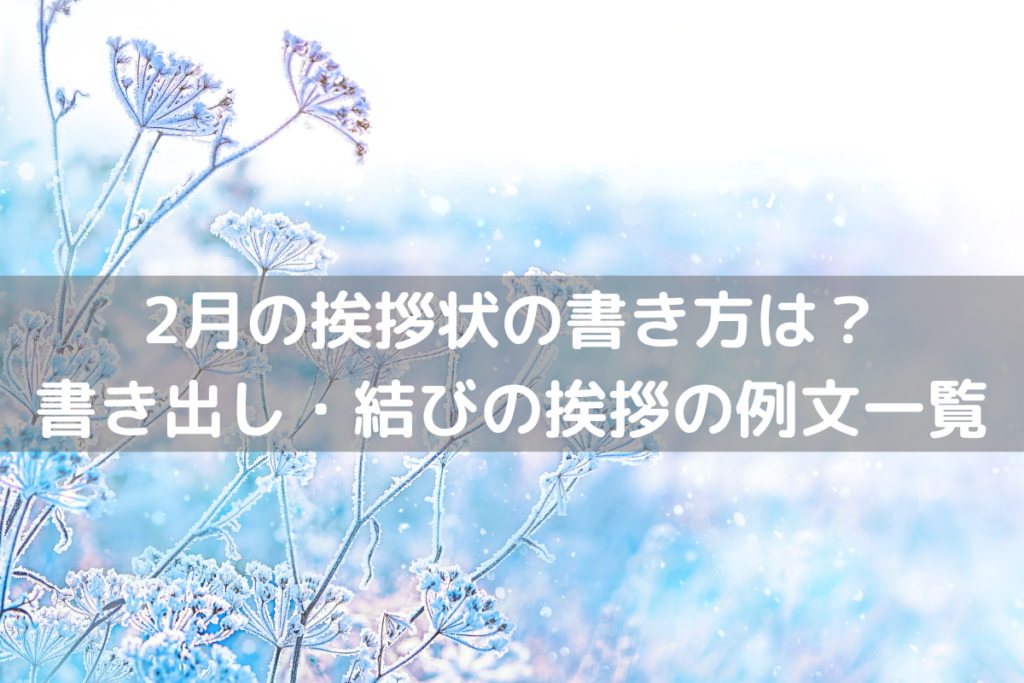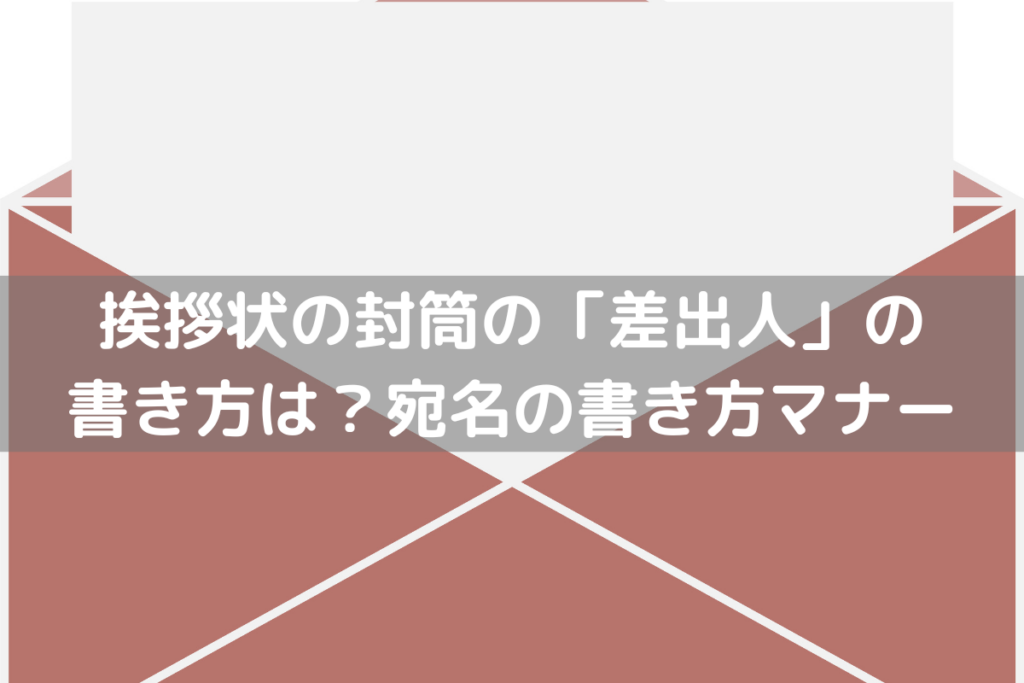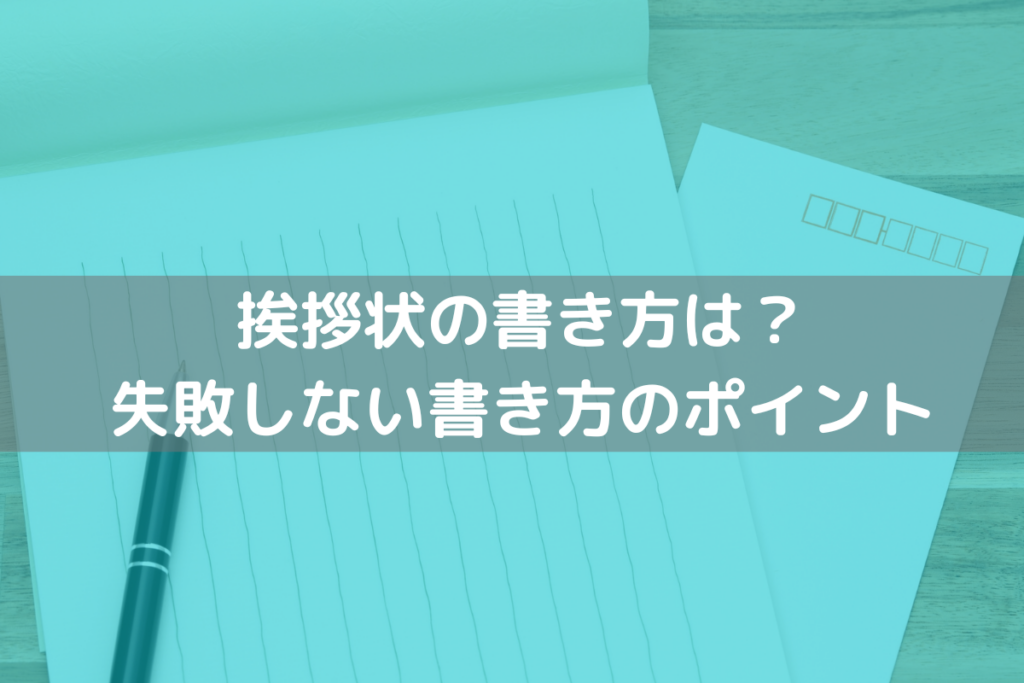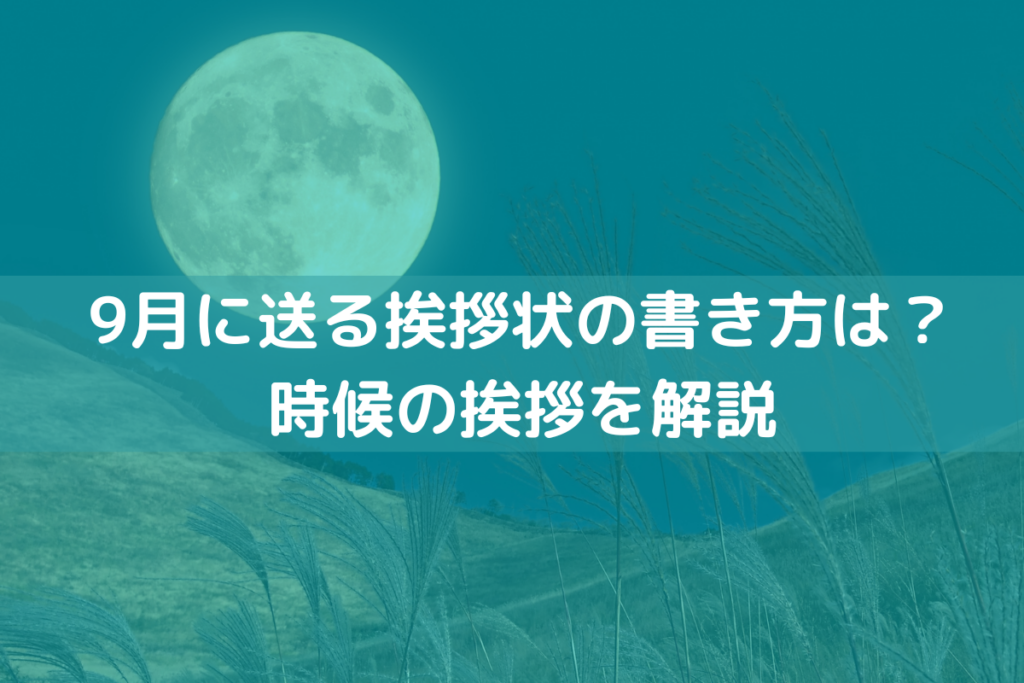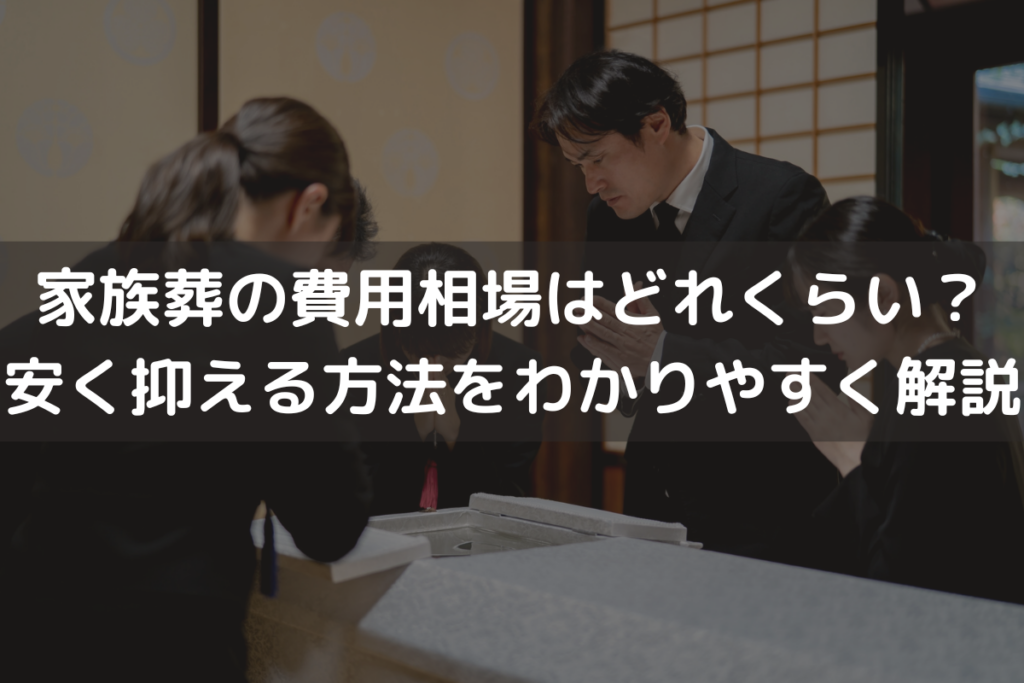
挨拶状を送る場面は少なくなっているものの、今も弔事の場面では挨拶状が多く活用されています。
では、法要や法事の挨拶状はどのように作成すればよいのでしょうか?また、法要や法事の挨拶状の作成では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
今回は、法要や法事で使える挨拶状の例文を多く紹介するとともに、挨拶状作成時に注意すべき点などをまとめて解説します。

法要・法事の挨拶状とは
家族が亡くなると、複数回の法要・法事が執り行われます。もともとは、次の法要・法事が営まれていました。
- 初七日法要:命日から7日目に行う法要
- 二七日法要:命日から14日目に行う法要
- 三七日法要:命日から21日目に行う法要
- 四七日法要:命日から28日目に行う法要
- 五七日法要:命日から35日目に行う法要
- 六七日法要:命日から42日目に行う法要
- 七七日(四十九日)法要:命日から49日目に行う法要
- 百か日法要:命日から100日目に行う法要
- 新盆法要:忌明け後最初に迎えるお盆に行う法要
- 一周忌法要:亡くなってから1年目に行う法要
- 三回忌法要:亡くなってから2年目に行う法要
- 三十三回忌法要:亡くなってから32年目に行う法要
近年では多忙な人が増えたことや弔いへの向き合い方が変化してきたことなどにより、これらすべて法要を営むことは少ないでしょう。ただし、次の法要は今も営まれることが一般的です。
- 初七日法要(葬儀当日に繰り上げて行うことが多い)
- 七七日(四十九日法要)
- 一周忌法要
- 三回忌法要
そして、これらを執り行う際は参列者に日程の連絡をしたり、近親者だけで執り行う場合は無事に法要を終えたことを報告したりします。これらに用いられるのが、法要・法事の挨拶状です。

法要・法事の挨拶状の例文
ここでは、法要や法事の挨拶状の例文をケースごとに紹介します。実際に挨拶状を作成する際の参考としてください。
四十九日法要を知らせる挨拶状
四十九日法要の案内をする挨拶状の例文は、次のとおりです。なお、四十九日法要を「七七日法要」や「満中陰法要」などと呼ぶこともあり、いずれも同じ法要を意味します。
謹啓 皆様におかれましてはご健勝にお過ごしのことと存じます
このたび左記日程にて亡父 挨拶太郎の四十九日法要を相営むこととなりました
つきましてはご多用中誠に恐縮ではございますが
ぜひともご臨席賜りたくご案内申し上げます 謹 白
記
日時 令和6年〇月〇日(〇曜日) 午前〇時より
会場 〇〇〇〇寺(住所 東京都〇〇区〇〇1-1-1)
電話番号 03-XXXX-XXXX
なお 法要後にささやかではございますが会食の席をご用意しております
以上
令和6年〇月〇日
施主 挨拶一郎
誠に恐縮でございますが〇月〇日まで同封のはがきにてご都合をご連絡いただきますようお願い申し上げます
いつ、誰のどのような法要をどこで営むのかを明確に伝えるとともに、ぜひ出席してほしい旨を記載します。また、往復はがきを使って出欠の連絡をもらうようにすると、集計がスムーズとなります。
四十九日法要を無事に終えたことを知らせる挨拶状
四十九日法要は近親者のみで営み、その他の相手には無事に忌明けを迎えた報告のみをすることもあります。この場合における挨拶状は、戒名を記載する場合と記載しない場合とで、それぞれ次のとおりです。
戒名がある場合
戒名がある場合の例文は、次のとおりです。
謹啓 亡父太郎儀 葬儀に際しましてはご多用中にもかかわらず御懇篤なる御弔慰を賜り 誠に有難く厚く御礼申し上げます
お陰をもちましてこのたび
〇〇〇〇〇〇〇(戒名)
四十九日の法要を滞りなく相営みました
早速拝眉の上御礼申し上げるべきところ
略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます 謹 白
令和6年〇月
施主 挨拶一郎
葬儀にて受けた弔慰(故人を弔い、遺族を慰めること)にお礼を伝えるとともに、四十九日法要を無事に済ませた旨を記載します。
戒名がない場合
戒名がない場合の例文は、次のとおりです。
謹啓 亡父太郎儀 葬儀に際しましてはご多用中にもかかわらず御懇篤なる御弔慰を賜り 誠に有難く厚く御礼申し上げます
お陰をもちましてこのたび四十九日の法要を滞りなく相営みました
早速拝眉の上御礼申し上げるべきところ
失礼ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます 謹 白
令和6年〇月
施主 挨拶一郎
戒名がない場合の文例も、戒名がある場合と大きく異なるものではありません。戒名がない場合には戒名部分を詰め、文章がつながるように記載します。
四十九日法要を無事に終えたことを知らせるとともに香典返しを送る場合の挨拶状
葬儀の際に香典を頂いている場合には、四十九日の忌明けのタイミングで香典返しをするのが原則です。そのため、四十九日法要を終えた報告をする挨拶状は、香典返しの挨拶状を兼ねることが少なくありません。この場合における例文は次のとおりです。
謹啓 亡父太郎儀 葬儀に際しましては ご多用中にもかかわらず御懇篤なる御弔慰ならびに御鄭重なる御厚志賜り 誠に有難く厚く御礼申し上げます
お陰をもちましてこのたび
〇〇〇〇〇〇〇(戒名)
四十九日の法要を滞りなく相営みました
つきましては供養のしるしに心ばかりの品をお届けいたしましたので 何卒ご受納くださいますようお願い申し上げます
早速拝眉の上御礼申し上げるべきところ
略儀ながら書中をもちまして御礼かたがたご挨拶申し上げます 謹 白
令和6年〇月
施主 挨拶一郎
葬儀参列のお礼や香典(「御厚志」などと表現します)などのお礼を伝えるとともに、香典返し(「心ばかりの品」などと表現します)を送る旨を記載します。
なお、これは戒名を記載する場合の例文です。戒名がない場合には戒名部分を省き、前後の文章をつなげます。
一周忌法要を知らせる挨拶状
一周忌法要の案内をする挨拶状の例文は、次のとおりです。
謹啓 春暖の候 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます
このたび左記日程にて亡父 挨拶太郎の一周忌法要を相営むこととなりました
つきましてはご多用中のところ大変恐縮ではございますが
皆様のご臨席を賜りたく御案内申し上げます 謹 白
記
日時 令和6年〇月〇日(〇曜日) 午前〇時より
会場 〇〇〇〇寺(住所 東京都〇〇区〇〇1-1-1)
電話番号 03-XXXX-XXXX
なお 法要後に同会館にて粗宴のご用意がございます
以上
令和6年3月〇日
施主 挨拶一郎
誠に恐縮でございますが〇月〇日まで同封のはがきにてご都合をご連絡いただきますようお願い申し上げます
一周忌法要を無事に終えたことを知らせる挨拶状
一周忌法要に参列しなかった相手に対し、一周忌法要を無事に終えた旨を伝える挨拶状の例文は次のとおりです。
謹啓 桜花の候 皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます
さて このたび 亡父 挨拶太郎 の一周忌法要を家族のみで相済ませましたことご報告申し上げます
本来であれば皆様に御臨席賜るところではございますが 甚だ勝手ながらささやかに行わせていただきました
誠に恐縮ではございますがご理解頂ければ幸いでございます
故人が生前に賜りました御厚誼に心より御礼申し上げ
略儀ながら書中をもちまして御挨拶申し上げます 謹 白
令和7年4月
施主 挨拶一郎

法要・法事の挨拶状の基本構成
挨拶状を送り慣れていない人にとって、法要や法事の挨拶状は難しく感じるかもしれません。しかし、基本の構成さえ理解してしまえば、さほど難しいものではないでしょう。ここでは、先ほど紹介した例文を踏まえ、法事・法要の挨拶状の基本構成を紹介します。
頭語
はじめに、頭語を記載します。頭語とは、挨拶状の書き出しにつける定型的な表現です。
頭語にはさまざまな種類があるものの、よく使われるものは「拝啓」と「謹啓」の2つです。「拝啓」はもっとも一般的な頭語であり広く使用できる一方で、「謹啓」はよりかしこまった表現となります。
安否の挨拶
頭語に続けて、安否の挨拶を記載します。「皆様益々ご清祥のことと存じます」や、「皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます」などの表現です。
「ご清祥」とは幸福や健康に過ごすこと、「ご健勝」とは健康で元気に過ごすことを指し、いずれを使用しても構いません。
なお、一般的な挨拶状では慶事の「慶」の字を使って「ご健勝のこととお慶び申し上げます」との表現をよく使用します。法要や法事の挨拶状はご逝去間もない時期に送るものではないものの、やはり慶事をイメージさせる「慶」を使うことに抵抗がある場合には「喜」を使うとよいでしょう。
本文
続けて、本文を記載します。法要の案内をする場合には、次の内容が分かるよう明確に記載します。
- 誰の法要であるのか
- 法要は、いつ、どこで行うのか
一方、無事に法要を終えたお礼を伝える場合には、次の内容を記載します。
- 無事に法要を終えた旨
- 相手へのお礼
あまり冗長とならないよう、必要な事項を簡潔に記載するとよいでしょう。
締めの挨拶
本文に続けて、締めの挨拶を記載します。法要・法事の案内である場合には、法要への出席(丁寧な表現で「ご臨席」といいます)をお願いしたい旨を記載することが多いでしょう。
一方、無事に法要を終えた報告などである場合には、暑中での挨拶を詫びる一文を入れることが一般的です。
結語
最後に、結語を記載します。結語は頭語に対応するものであり、頭語に対応する表現を使います。一般的な組み合わせは、それぞれ次のとおりです。
- 頭語が「拝啓」の場合:「敬具」、「敬白」
- 頭語が「謹啓」の場合:「謹白」、「謹言」
組み合わせを誤るとちぐはぐな印象となってしまうため、ご注意ください。

法要・法事の挨拶状を作成する際の注意点
法要・法事の挨拶状作成ではどのような点に注意する必要があるのでしょうか?最後に、挨拶状作成の注意点をまとめて解説します。
- 時候の挨拶は記載しない
- 縦書きでの作成が基本
- 句読点は使わない
- 誤字脱字をしない
時候の挨拶は記載しない
挨拶状では、「陽春の候」や「風薫るころとなりましたがいかがお過ごしでしょうか」などの時候の挨拶を記載することが一般的です。
一方で、ご逝去から日の浅い時期に送る弔事にまつわる挨拶状では、これらの時候の挨拶を省くのが通例とされています。ただし、四十九日の忌明け以降に送る挨拶状では、時候の挨拶を記載しても構いません。
縦書きでの作成が基本
挨拶状は、縦書きで作成するのが基本です。近年では比較的カジュアルな場面で送る挨拶状を中心に、横書きされるケースも散見されるようになりました。しかし、法要・法事の挨拶状を横書きにすることは、今も一般的ではありません。
句読点は使わない
挨拶状では、句読点を使用しないのが基本です。これは、日本古来の挨拶状という風習に、比較的新しい文化である句読点が馴染まないとの考えによるものです。
とはいえ、縦書き・横書きと同じく、近年では挨拶状で句読点を使うこともさほどめずらしくなくなっています。しかし、法要などの挨拶状で句読点を使うことは今も一般的ではないため、特に理由がない限りは避けたほうがよいでしょう。
誤字脱字をしない
法要・法事の挨拶状に限ったものではありませんが、挨拶状の作成では誤字脱字に十分注意しなければなりません。特に、相手の氏名などの誤りは大変失礼にあたるため、何度も確認してから印刷することをおすすめします。
なお、印刷後に誤字や脱字に気付いた場合、修正テープや二重線などで直すことはマナー違反です。
手間であっても、修正した内容で改めて印刷しなおしましょう。

まとめ
法要・法事の挨拶状の例文を紹介するとともに、基本構成や注意すべきポイントなどを解説しました。
法要など弔事の場面では、今も挨拶状が多く使用されています。しかし、挨拶状にはさまざまなマナーや独特の言い回しなどが存在するため、挨拶状に慣れていない人は戸惑ってしまうかもしれません。その際は、「挨拶状印刷.jp」の活用がおすすめです。
「挨拶状印刷.jp」では、法要などの挨拶状のテンプレートを数多くご用意しており、挨拶状を簡単に作成できます。また、オプションで宛名印刷や投函代行も可能です。法要・法事の挨拶状作成でお困りの際は、挨拶状印刷.jpをご活用ください。