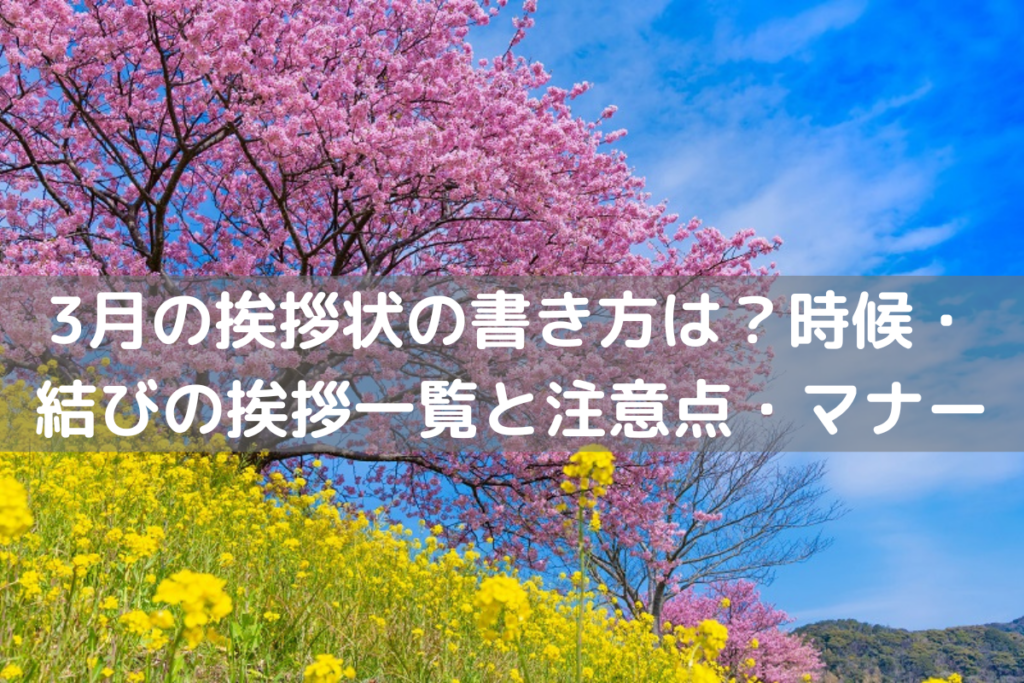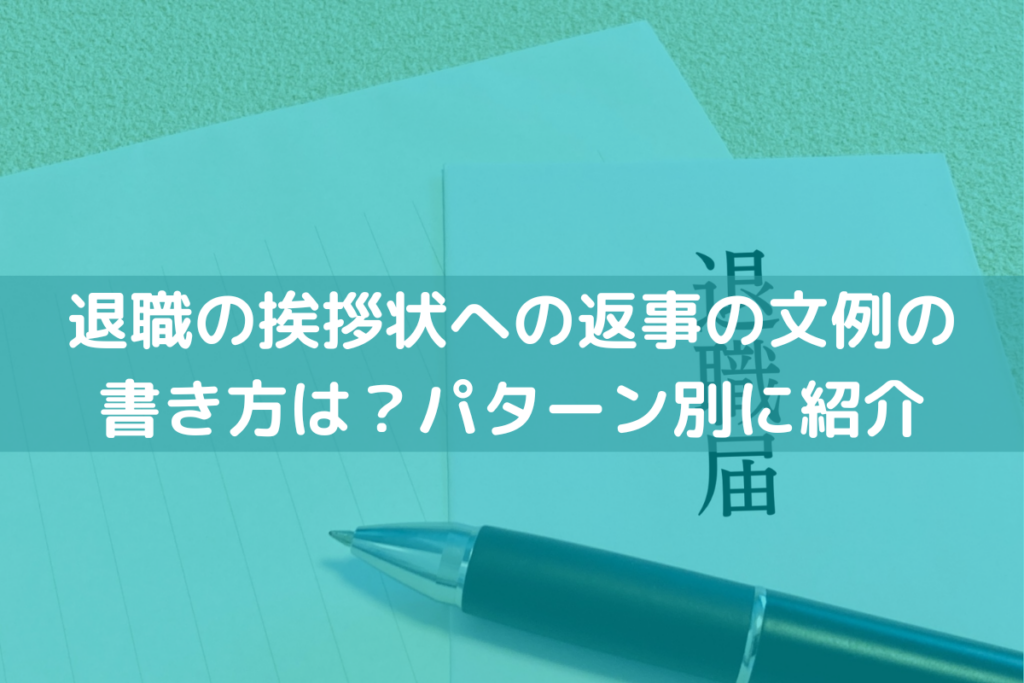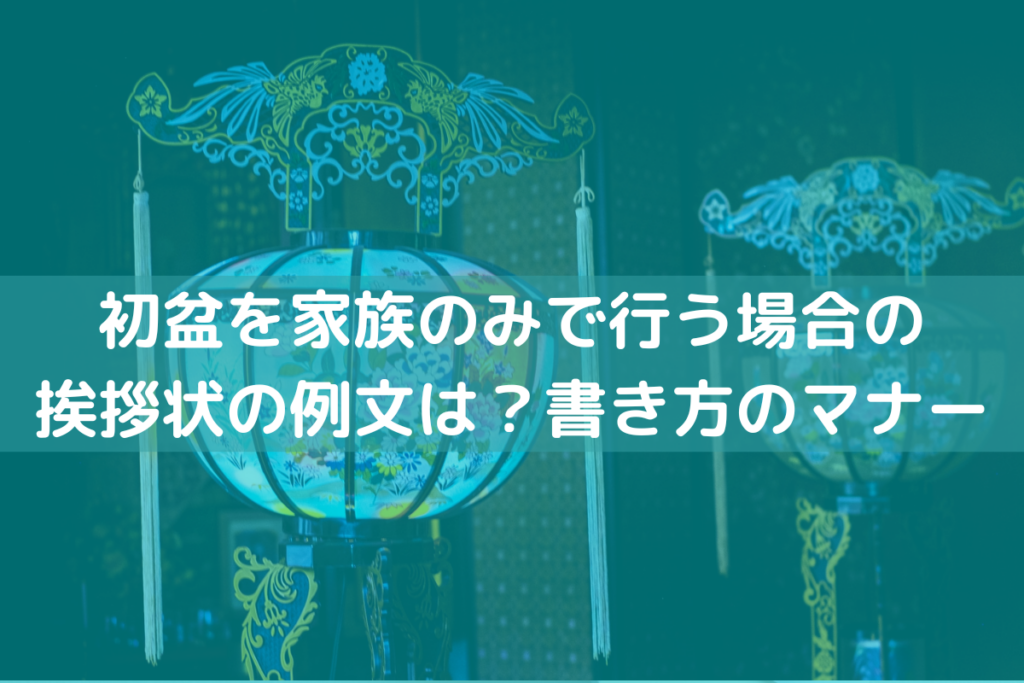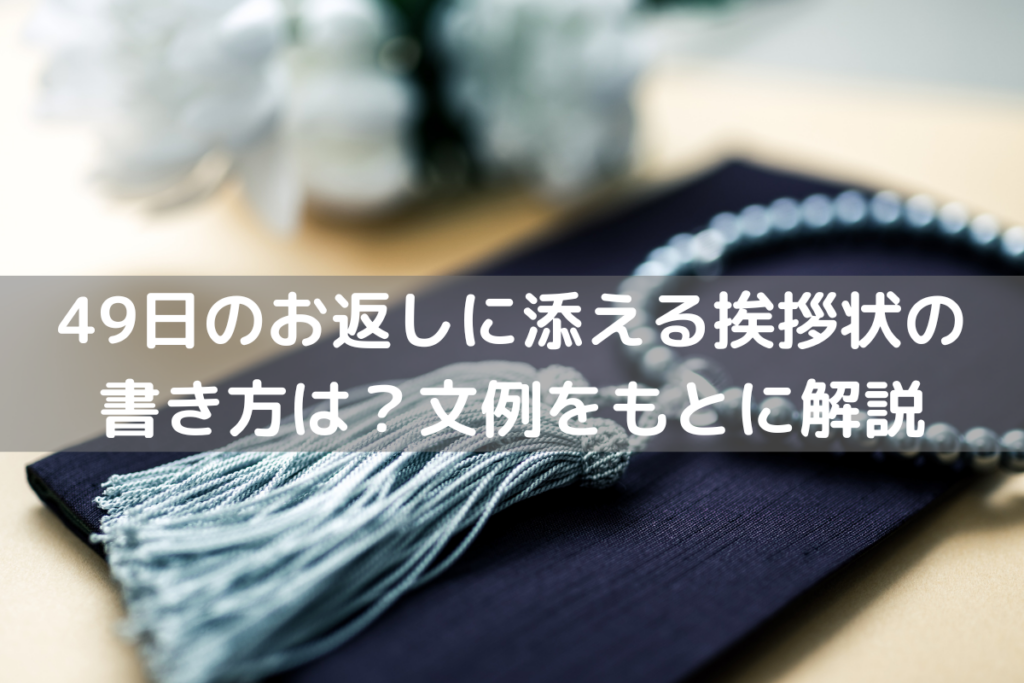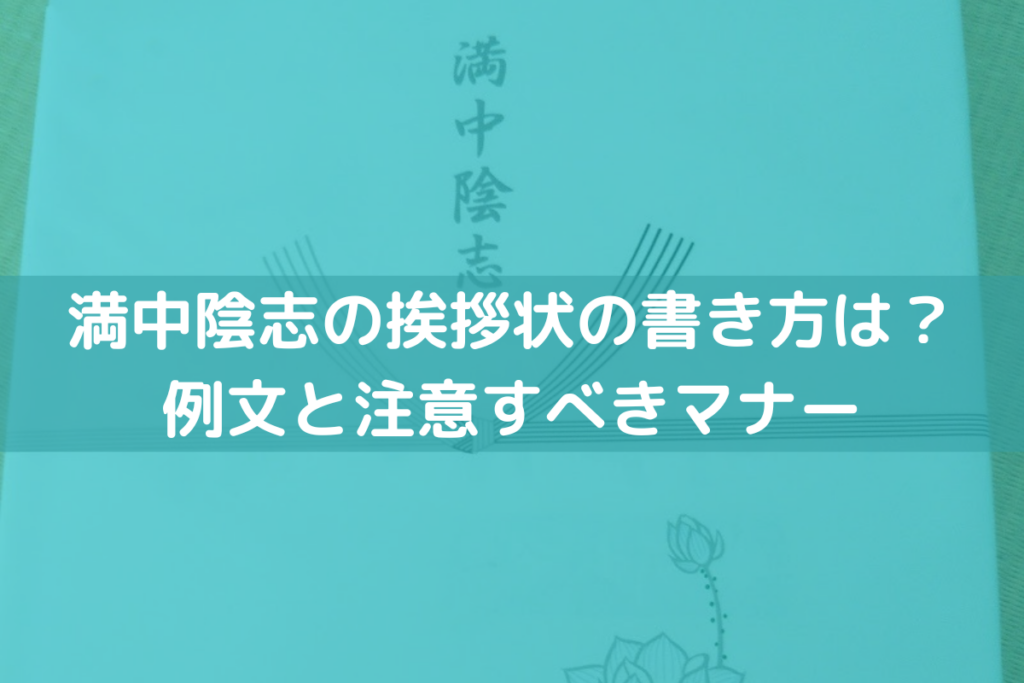身内に不幸があった際は、年賀状などの代わりに喪中の挨拶状を贈ることが基本です。
では、喪中の挨拶状は、いつ誰に送ればよいのでしょうか?また、喪中の挨拶状の文面は、どのようなものが適切なのでしょうか?
今回は、喪中の挨拶状の基本を解説するとともに、喪中挨拶状の文例を紹介します。
なお、当サイト「挨拶状印刷.jp」ではさまざまなシーンで活用できる挨拶状のテンプレートを数多く取り揃えており、喪中の挨拶状についてもご用意があります。マナーに即した喪中挨拶状の作成でお困りの際は、挨拶状印刷.jpをご活用ください。

喪中の挨拶状とは
喪中の挨拶状とは、自身が喪中であることを理由に新年の挨拶を控えることを知らせる挨拶状です。
身内が亡くなってからおおよそ1年間は「喪中」にあたり、この期間は慶事への参加を控えるべきとされています。そのため、新年を祝う年賀状の送付も、控えることが基本です。
しかし、毎年年賀状をやり取りしている相手から年賀状が送られて来なければ、相手が不審に感じたり心配したりするかもしれません。そこで、あらかじめ喪中の挨拶状を送り、新年の挨拶を控えることを相手に伝えるのがマナーとされています。

喪中の挨拶状の基本
喪中の挨拶状は、いつ誰に送ればよいのでしょうか?ここでは、喪中の挨拶状の基本マナーについて解説します。
喪中挨拶状は誰が亡くなったときに送る?
喪中の挨拶状を送るのは、原則として、次の人が亡くなった場合です。
- 配偶者(夫・妻)
- 父母・義父母
- 祖父母・義祖父母
- 子ども・子どもの配偶者
- 兄弟姉妹
ただし、同居しておらず縁が遠くなっている祖父母や義祖父母などの場合には通常どおり年賀状を送り、喪中の挨拶状を送らない場合もあります。さほど厳格な決まりはないため、亡くなった人と別居していた場合には、自身が喪に服す気持ちがある(年賀状の送付に抵抗がある)場合に喪中挨拶状を送るとよいでしょう。
喪中挨拶状はいつ送る?
喪中の挨拶状を送る時期は、それぞれ次のとおりです。
原則:11月から12月初旬頃に送る
喪中の挨拶状は、11月から12月初旬に送ることが基本です。なぜなら、これより遅くなると相手方がすでに年賀状を用意している可能性が高くなるためです。
喪中の相手に年賀状を送るのはマナー違反ではないものの、一般的には控えることが多いでしょう。相手がすでに年賀状を差し出している時期に喪中の挨拶状を送った場合、相手に気を遣わせてしまうかもしれません。
12月に亡くなった場合:1月7日以降に寒中見舞いを送る
12月に身内が亡くなった場合、12月初旬までに喪中の挨拶状を送ることは困難です。この場合は無理に年内に挨拶状を送らず、松の内(1月7日頃)以後に寒中見舞いを送ります。
松の内以降に喪中の挨拶状を送る場合には、新年の挨拶ができなかったお詫びと、年賀状をいただいたお礼などを記載するとよいでしょう。
喪中挨拶状は誰に送る?
喪中の挨拶状を送る相手の範囲に、厳格な決まりはありません。一般的には、日ごろ年賀状のやり取りをしている相手に送るとよいでしょう。

【ケース別】喪中挨拶状の例文
喪中の挨拶状は、どのような文面にすればよいのでしょうか?ここでは、基本の例文を、ケース別に7つ紹介します。
挨拶状印刷.jpは、さまざまなシーンで活用できる挨拶状のテンプレートを多く取り揃えており、喪中挨拶状についても取り揃えています。喪中挨拶状の作成でお困りの際は、挨拶状印刷.jpをご活用ください。
基本の例文
喪中の挨拶状の基本となる例文は、次のとおりです。
喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます
本年〇月に父 太郎が〇〇歳にて永眠いたしました
本年中に賜りましたご厚情に感謝致しますとともに
皆様が健やかなる新年をお迎えになりますようお祈り申し上げます
令和〇年〇月
身内(例では、父)が亡くなったことを伝えるとともに、相手の健康を願う内容としています。
なお、友人などに送る際は、最後の一文と「明年も変わらぬご交誼のほどをお願い申し上げます」などとしてもよいでしょう。「ご交誼」とは、友人としての親しい付き合いを丁寧に伝える表現です。
近親者で葬儀を済ませたことを記載する例文
喪中の挨拶状では、近親者ですでに葬儀を済ませたことを記載する場合もあります。この場合の例文は、次のとおりです。
喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます
本年〇月に父 太郎が〇〇歳にて永眠いたしました
なお 葬儀は故人の希望により近親者のみにて執り行いました
ご通知が遅れましたこと深くお詫び申し上げます
生前賜りましたご厚情に心より御礼申し上げますとともに
皆様が健やかなる新年をお迎えになりますよう心よりお祈り申し上げます
令和〇年〇月
葬儀を済ませたことを喪中の挨拶状で知らせる場合には、通知が遅れたことを詫びる一文を入れるとよいでしょう。
故人が2人いる場合の例文
同じ年に父と母が亡くなった場合など、故人が2人いる場合もあります。この場合における喪中の挨拶状の例文は、次のとおりです。
喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます
本年〇月に父 太郎が〇〇歳にて
〇月に母 花子が〇〇歳にて永眠いたしました
本年中に賜りましたご厚情に感謝致しますとともに
皆様が健やかなる新年をお迎えになりますようお祈り申し上げます
令和〇年〇月
故人が2人いる場合には、このようにそれぞれの名前と享年を記載します。
カトリックの場合の例文
キリスト教には喪中の概念はありません。しかし、年始の挨拶を控えたい場合には、喪中はがきにあたる挨拶状を出すとよいでしょう。カトリックの場合における喪中挨拶状の例文は、次のとおりです。
新年のご挨拶に代えて
本年〇月に父 太郎が〇〇歳にて帰天いたしました
生前に賜りましたご厚情に深謝致しますとともに
皆様に幸多き年が訪れますよう心よりお祈り申し上げます
令和〇年〇月
カトリックの場合、「喪中」という表現は使用しません。また、亡くなることを「帰天」と表現します。
プロテスタントの場合の例文
プロテスタントの場合における喪中はがきにあたる挨拶状の例文は、次のとおりです。
新年のご挨拶に代えて
本年〇月に父 太郎が〇〇歳にて天に召されました
生前に賜りましたご厚情に深謝致しますとともに
皆様に幸多き年が訪れますよう心よりお祈り申し上げます
令和〇年〇月
プロテスタントの場合には、亡くなることを「天に召された」や「召天」などと記載します。その他の文面は、一般的なものと大きな違いはありません。
法人から差し出す場合の例文
法人には喪中の概念がなく、社長の近親者が亡くなった場合であっても通常どおり年賀状を出すことが原則です。
ただし、社長や会長が亡くなった場合などには、会社から喪中の挨拶状を送ることもあります。その場合における例文は、次のとおりです。
喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます
本年〇月 弊社会長の挨拶太郎が〇〇歳にて永眠いたしました
生前に賜りましたご厚情に深謝致しますとともに
今後とも変わらぬご支援ご鞭撻のほどお願い申し上げます
令和〇年〇月
ただし、法人が喪中の挨拶状を送った場合、取引先などに気を遣わせてしまう可能性もあるでしょう。そのため、喪中の挨拶状を送るか否かや、送る場合にはその範囲などをあらかじめ検討することをおすすめします。
寒中見舞いとして送る場合の例文
先ほど解説したように、12月に亡くなった場合などには、松の内以降に寒中見舞いを送付することが一般的です。この場合における寒中見舞いの例文は、次のとおりです。
寒中お見舞い申し上げます
ご丁寧なお年始状をいただき誠にありがとうございました
令和〇年12月に父 太郎が〇〇歳にて永眠いたしましたため
年頭のご挨拶を控えさせていただきました
本来であれば旧年中にお知らせすべきところ
ご連絡が行き届かず申し訳ございません
寒さ厳しき折柄 皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます
令和〇年一月
寒中見舞いとして喪中の挨拶状を送る場合には、年賀状をいただいたお礼を伝えるとともに、連絡が遅れたことを詫びる一文を入れるとよいでしょう。また、寒中見舞いであることから、相手の健康を気遣う文言を記載します。

喪中の挨拶状の基本構成
喪中の挨拶状は、基本構成を抑えれば難しいものではありません。ここでは、喪中挨拶状の基本構成を解説します。
- 書き出し
- 誰がいつ亡くなったのか
- お礼の言葉
- 結びの挨拶
書き出し
はじめに、喪中であることがわかる一文を記載します。たとえば、「喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます」や「喪中につき年末年始のご挨拶を失礼させていただきます」などです。なお、「年賀」はおめでたい場合に使用する表現であるため、避けた方が無難です。
誰がいつ亡くなったのか
続けて、誰がいつ亡くなったのかを記載します。「本年〇月に父 太郎が〇〇歳にて永眠いたしました」などです。信仰する宗教によっては、「帰天いたしました」や「天に召されました」などと表現することもあります。
お礼の言葉
次に、相手へのお礼の言葉を記載します。故人とのかかわりが深かった相手には「生前に賜りましたご厚情に深謝致します」など、自身との関わりが深い相手には「本年中に賜りましたご厚情に感謝致します」などとするとよいでしょう。
結びの挨拶
最後に、結びの挨拶を記載します。結びの挨拶は、相手の健康や幸せを願う内容のほか、よい年を迎えるよう祈る内容などを記載するのが一般的です。
たとえば、次の表現などが挙げられます。
- 皆様が健やかなる新年をお迎えになりますよう心よりお祈り申し上げます
- 皆様に幸多き年が訪れますよう心よりお祈り申し上げます
- みなさまには良い年が訪れますようお祈りいたします
また、相手が友人などであれば、「明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます」など変わらぬ付き合いをお願いする内容を記載することもあります。

喪中の挨拶状のマナー
最後に、喪中の挨拶状の基本マナーをまとめて紹介します。
- 縦書きで作成する
- 句読点は使わない
- おめでたい言葉の使用を避ける
- 添え書きはしない
縦書きで作成する
近年では年賀状を横書きとするケースが散見される一方で、喪中の挨拶状は縦書きで作成することが基本です。ただし、キリスト教などの場合には日本の伝統にとらわれず、横書きとする場合もあります。
句読点は使わない
喪中の挨拶状には、原則として句読点は使用しません。これは、挨拶状など縦書きで作成される日本の伝統的な文書には、句読点がそぐわないとされるためです。
なお、これは喪中の挨拶状に限ったことではなく、年賀状であっても同様です。
おめでたい言葉の使用を避ける
喪中の挨拶状では、おめでたい言葉の使用は避けましょう。避けるべき表現は、「年賀」や「あけましておめでとうございます」、「お慶び」などです。
添え書きはしない
親しい相手に送る年賀状では、近況報告などを添え書きすることがあります。一方で、喪中の挨拶状には原則として添え書きは行いません。近況報告などをしたい場合には、喪中挨拶状に記載するのではなく、別途連絡を取って行うとよいでしょう。

まとめ
喪中の挨拶状の基本や基本構成、マナーを解説するとともに、ケース別の文例を紹介しました。
喪中の挨拶状とは、喪中の場合に新年の挨拶を控えることを知らせる挨拶状です。喪中の挨拶状は相手が年賀状の準備を始める11月から12月初旬頃までに送ります。
ただし、年末に亡くなった場合などにはこの時期の送付が困難であるため、松の内以降に寒中見舞いで喪中を伝えるとよいでしょう。
喪中の挨拶状では、喪中により新年の挨拶を控えることのほか、誰がいつ亡くなったのかなどの情報を記載します。喪中の挨拶状の文面はある程度定型的であるため、テンプレートを活用することでスムーズに作成できます。
挨拶状印刷.jpではさまざまなシーンで活用できる挨拶状のテンプレートを数多く掲載しており、喪中の挨拶状についても数多くの文例を用意しています。また、オプションで宛名印刷や投函代行も可能です。
喪中の挨拶状の作成には、ぜひ挨拶状印刷.jpのサービスをご利用ください。